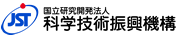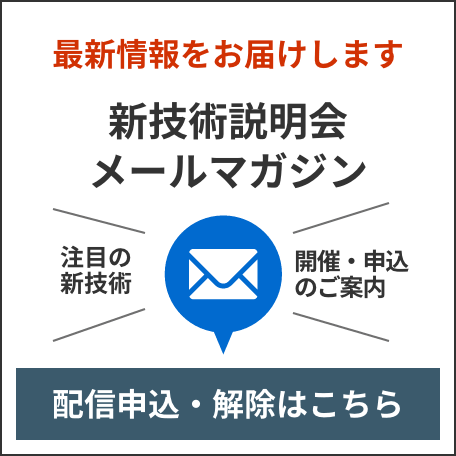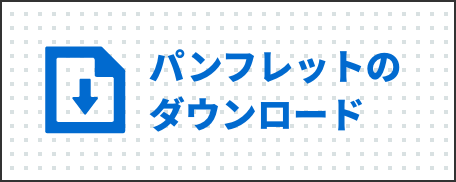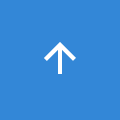首都圏北部4大学発 新技術説明会(2)
日時:2013年06月07日(金)
会場:JST東京別館ホール(東京・市ヶ谷)
参加費:無料
発表内容一覧
発表内容詳細
- 環境
1)固体表面から放射性物質を除染するための高分子水溶液
茨城大学 工学部 物質工学領域 准教授 熊沢 紀之
新技術の概要
放射性物質により汚染されたコンクリート、屋根瓦、金属表面等から簡便に除染するための高分子水溶液とその利用方法。
従来技術・競合技術との比較
表面研磨による除染と比べて粉塵がなく、既存の剥離剤の様に有機溶媒を使用しないため、環境負荷が小さい。
新技術の特徴
・多様な表面からの除染に広く利用可能で作業効率も高い
・放射性セシウムを保持する機能が高い
・廃棄物の減容化が可能である
想定される用途
・屋根瓦、コンクリート、金属表面等からの除染
・高線量の福島第一建屋内で粉塵除去、除染
・汚染表面からの粉塵抑制
関連情報
・サンプルの提供可能
・展示品あり(サンプルを視聴者へ提示します)
- エネルギー
2)塗布型有機薄膜太陽電池の実現に向けた静電塗布法の成膜技術としての確立
埼玉大学 大学院理工学研究科 物理機能系専攻 助教 福田 武司
新技術の概要
静電塗布法は高電圧の印加で溶液を噴射する技術であるが、溶液の各種パラメータの最適化や装置設計などを考慮することで、新しい成膜技術として確立されてきた。これまでに溶媒蒸気圧の最適化などによって有機薄膜の表面平坦性を改善し、各種有機デバイスを実現してきた。
従来技術・競合技術との比較
従来の塗布技術では低濃度の溶液を成膜したときに有機薄膜太陽電池で必要な100?200nm程度の膜厚を実現することが困難である。また、同一溶媒で溶ける材料の積層が出来なかった。静電塗布法ではこれらの問題を解決できる。
新技術の特徴
・高粘度の材料の塗布成膜が可能である
・低濃度の溶液の塗布成膜が可能である
想定される用途
・マイクロマシンなどの厚膜のレジスト塗布の分野
・有機薄膜の成膜が要求される電子デバイス分野
・バイオエレクトロニクス分野
- エネルギー
3)振動利用システムに発生する低周波振動の防止対策の構築
埼玉大学 大学院理工学研究科 連携先端・重点研究部門 准教授 森 博輝
新技術の概要
振動ふるいなどの振動利用システムで発生しうる異常振動をシミュレーション可能な解析モデルを開発した。これにより異常振動を防止するための効率的な防止対策を構築することができる。
従来技術・競合技術との比較
低周波振動の問題が生じた機械ごとにダンパ追加を行う従来の手法に対して、本技術では設計段階で振動を防止するための指針を得ることができる。既存のシステムに対しても、低コストの効率的な対応が可能である。
新技術の特徴
・振動のメカニズムに基づいた根本的な対策が可能
・既存のシステムに生じる問題に対して効率的な対応が可能
・振動機械の主要なパラメータに関する振動発生判別マップが作成可能
想定される用途
・振動機械(振動ふるい等)の設計指針の確立
・低周波振動防止装置の設計
・振動機械の健全性の評価
- 創薬
4)新規抗がん剤と抗トリパノソーマ原虫剤の開発
群馬大学 生体調節研究所 遺伝子情報分野 准教授 久保原 禅
新技術の概要
我々は、土壌微生物「細胞性粘菌」由来のポリケチドの1つDIFとその誘導体が抗腫瘍活性(in vitroでの増殖抑制/遊走阻害活性)を有することを発見した。さらに、一部のDIF誘導体が抗トリパノソーマ原虫活性を有することを見出し、in vivoにおける薬効も確認した。
従来技術・競合技術との比較
がんの浸潤・転移を抑制する抗がん剤は開発途上にある。また、トリパノソーマ原虫に起因する疾病(南米シャーガス病等)の治療薬開発も遅れている。DIF誘導体は、がん細胞の増殖、浸潤・転移を阻害する抗がん剤および抗トリパノソーマ剤のリード化合物として期待される。
新技術の特徴
・がん細胞の浸潤・転移を阻害する薬剤
・トリパノソーマ症の治療
・未開拓創薬資源「細胞性粘菌」由来の化合物
想定される用途
・抗がん剤
・抗トリパノソーマ剤
・基礎研究試薬
関連情報
・サンプルの提供可能
- 医療・福祉
5)生体組織と自己接合する挿入管構造とその接合方式
茨城大学 工学部 機械工学領域 教授 増澤 徹
新技術の概要
人工心臓に代表される人工臓器の開発が進み、カテーテルや脱血管を生体組織に接合する機会が増えている。本特許では複合低エネルギー接合方式を応用した生体組織へ簡便、安全に接合可能な挿入管を提案する。
従来技術・競合技術との比較
従来は人工管を生体組織に接合するためには糸による結紮しか方法がなかった。本方法は低レベルの熱と圧力を与えることで人工管を生体組織に自己接合するまったく新規な方法である。本方法を用いることで簡便、強固な接合ならびに感染防止のための封止接合が可能となる。
新技術の特徴
・人工管を生体組織に接合するためのまったく新規な方法
・簡便、強固な接合ならびに感染防止のための封止接合が可能
・低エネルギー利用であるため身体にやさしい
想定される用途
・人工心臓などの人工臓器の脱血管
・人工心臓などの体外から体内への電力伝送用ケーブル導管
・その他、体内外の液体、気体などの輸送管
関連情報
・外国出願特許あり
- アグリ・バイオ
6)含ケイ素高発光型蛍光物質を用いた蛍光プローブの開発
群馬大学 理工学研究院 分子科学部門 准教授 森口 朋尚
新技術の概要
ケイ素導入ピレンを新規蛍光物質として用いたDNAやコレステロールなどの生体関連物質の蛍光プローブについて紹介する。高発光型蛍光物質を用いることで、より高感度での生体関連物質の細胞内挙動を観測できる。
従来技術・競合技術との比較
従来から用いられている蛍光プローブは、感度が低かったり、検出に複雑な操作を必要とするなど、煩雑な点があった。本技術では検出対象にプローブを添加するだけで、対象となる生体関連物質の検出が可能となる。
新技術の特徴
・合成が容易であるため、様々な官能基を導入することが可能
・溶液、薄膜などのサンプルの形状に依存しない
・脂溶性が高いため、有機溶媒中での蛍光標識化が可能
想定される用途
・機能未解明な生体関連物質の細胞内挙動の解明
・微量サンプルを用いた高感度遺伝子検出
・遺伝子疾患の原因となる一塩基変異の高感度検出
関連情報
・サンプルの提供可能
- 材料
7)オンデマンド乾式高速レーザめっき(HLP)技術
茨城大学 工学部 機械工学領域 教授 前川 克廣
新技術の概要
電気めっき、化学めっきを代替しうる成膜技術として高速レーザめっき(HLP)法 を開発した。必要箇所に塗布した金属ナノ粒子ペーストをレーザ照射により焼結することを特徴とする。金や銀のナノ粒子を用いて、膜厚0.5?3ミクロンの基材との密着性に優れた緻密膜を形成することができる。基材の前処理、後処理を不要とし、大気中で全工程5?20分の部分めっきバッチ処理が小規模設備投資で可能となる。
従来技術・競合技術との比較
本技術は、電気めっき、化学めっきなどの従来めっき技術と競合する。従来法に比べて、部分めっきが小規模設備投資で可能、エンプラやセラミックスへのめっきも容易、省資源・低環境負荷などの優位性がある。一方、塗布した金属ナノ粒子ペーストを乾燥、炉焼成、あるいはUV照射する従来のインクジェット印刷やスクリーン印刷で課題となっている被膜の多孔質構造や基材との低密着性を、レーザ照射によって解決している。大面積めっき部品の大量少品種生産には、現状では不向きである。
新技術の特徴
・必要箇所に塗布した金属ナノ粒子ペーストをレーザ照射により焼結
・銀ナノ粒子ペーストによる膜厚0.5~3ミクロンの高密着性緻密膜を形成
・大気中で全工程(印刷→仮乾燥→レーザ焼結、前処理・後処理不要)5~20分
想定される用途
・電気めっき、化学めっき代替
・電子部品(部分めっき用、配線)
・フレキシブル有機デバイス
関連情報
・サンプルの提供可能
・展示品あり(サンプル)
- 材料
8)ケイ素の特性を利用した新規色素増感太陽電池の設計
群馬大学 理工学研究院 分子科学部門 教授 海野 雅史
新技術の概要
これまでに例のない含ケイ素色素を合成し、さらに、酸化チタンへ強固に結合することができるシラノールまたはアルコキシシランを用いることで、色素増感太陽電池の1)高効率化、2)耐久性の向上、3)製造コストの低減、を同時に達成し、高効率・高耐久性色素増感太陽電池を実現する。
従来技術・競合技術との比較
色素増感太陽電池はまだ実用化まで達していないが、単結晶シリコン系の太陽電池と比較し、効率では劣るものの、耐久性並びに製造コストにおいて優れており、新たな市場を形成する可能性がある。これまでに含ケイ素色素並びにシラノールを含む色素は検討されておらず、従来、競合技術とは一線を画する。
新技術の特徴
・含ケイ素色素の高い吸光度
・シラノールによる、酸化チタンとの高い結合力
・高真空または高温プロセスを必要としない製造コストの低減
想定される用途
・新規太陽電池デバイス
- 材料
9)半導体集積回路装置用バリア材の探索方法及びバリア材
茨城大学 工学部 物質工学領域 教授 篠嶋 妥
新技術の概要
なぜRuがCu配線のバリアメタル材として良い特性を示すのかを分子動力学法によるシミュレーションにより明らかにした。この知見をもとに新バリア材探索のための指針を立てた。第1原理計算により候補材の妥当性を確認した。
従来技術・競合技術との比較
従来は経験をベースとした多数の実験の積み重ねが必要であったのに対して、本技術は事前に計算機実験を行うことで候補材の絞り込みが可能である。
新技術の特徴
・シミュレーションによる原理に基づいた材料開発ができる
・事前に計算機実験を行うことで候補材の絞り込みが可能である
・広範囲の材料開発に適用できる
想定される用途
・LSI用新バリア材の開発
・薄膜材料の構造予測
・レアメタル代替材料の探索
- アグリ・バイオ
10)嵩高いシリル基の立体保護効果を利用したオリゴ糖合成の簡略化
埼玉大学 大学院理工学研究科 物質科学専攻 准教授 幡野 健
新技術の概要
本方法では、市販の無保護糖から一段階の反応によりオリゴ糖合成には欠かせない糖受容体を簡便に合成することができる。この受容体はC3位に位置特異的にグリコシル化反応することから、C3位へのグリコシル化反応が必要な3’シアリルラクトース(インフルエンザ結合糖鎖)などの生理活性オリゴ糖合成の反応ステップ数削減、コスト削減、環境負荷の低減が期待でき、安定なオリゴ糖の大量供給が可能と考えられる
従来技術・競合技術との比較
オリゴ糖の化学合成は、糖受容体と糖供与体のグリコシル化反応により行われる。糖受容体は、グリコシル化を受ける水酸基以外の水酸基を化学的に保護するのが定石である。そのため、必然的に糖水酸基の保護・脱保護を繰り返し行うこととなる。また、多くの糖誘導体は結晶性が良くなく、且つ熱的安定性も低いため、その精製にはカラムクロマトグラフィーが多用され、シリカゲル・溶媒の大量消費と多大な労力がオリゴ糖合成には伴う。これらがオリゴ糖を低価格で安定供給できない理由と考えられる。
新技術の特徴
・隣接水酸基の立体保護(速度論的安定化)
・反応ステップ数の大幅削減(合成の簡略化)
・新規薬剤・医療材料の開発研究の躍進と早期実用化
想定される用途
・生理活性オリゴ糖の化学合成
・糖合成中間体の化学合成
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
茨城大学 産学官連携イノベーション創成機構
TEL:0294-38-7281FAX:0294-38-5240Mail:ccrd-iu
 ml.ibaraki.ac.jp
ml.ibaraki.ac.jp宇都宮大学 知的財産センター
TEL:028-689-6318FAX:028-689-6320Mail:chizai
 miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp
miya.jm.utsunomiya-u.ac.jp群馬大学 群馬大学TLO
TEL:0277-30-1171FAX:0277-30-1178Mail:tlo
 ml.gunma-u.ac.jp
ml.gunma-u.ac.jp埼玉大学 オープンイノベーションセンター
TEL:048-858-3849FAX:048-858-9419Mail:coic-jimu
 ml.saitama-u.ac.jp
ml.saitama-u.ac.jp新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp