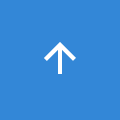福岡工業大学 新技術説明会
日時:2017年03月14日(火) 09:55~12:25
会場:JST東京本部別館1Fホール(東京・市ケ谷)
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、福岡工業大学
後援:特許庁
発表内容一覧
発表内容詳細
- 情報
1)最適三次元画像計測技術及びロボット、3Dプリンタ等分野への応用
福岡工業大学 工学部 電子情報工学科 教授 盧 存偉
新技術の概要
本技術は基本特許と幾つかの応用特許を含む。基本特許は1回のパターン光投影で3D画像計測を実現する最適パターン光投影三次元画像計測技術であり、日本・米国・中国に登録している。応用特許はそれぞれ非静止物体、光沢物体、高温物体などの種類別や、自動車部品、人体などの物体別への適用技術である。
従来技術・競合技術との比較
パターン光投影3D画像計測技術は非接触、確実に表面形状を取得できる。しかし従来技術では計測誤差を1%以内に抑えるために7回、0.1%以内には10回の投影が必要で、計測時間が長く、非静止物体への実用ができない。本技術はどの計測精度でも1回のパターン光投影しか必要としないので、上記の問題を徹底的に解決した。
新技術の特徴
・一回のパターン光投影しか必要としないので、計測速度が速く、非静止物体や人体の計測が可能である。
・レーザー不使用、パターン光切替不要なので、構造簡単、高速度・高精度・低コスト的な3D画像計測を構築できる。
・静止物体は勿論、非静止、超高温、光沢物体などパターン光投影計測に向かない特殊な物体の計測も可能。
想定される用途
・3Dロボットビジョン。従来のシステムと比べ、計測時間を1/3以下に抑えることができ、静止しなくても計測可能。
・車などの生産ライン、物流や倉庫などにおける品質検査。従来法では計測できない金属、陶磁器でも計測可能。
・3Dプリンターとの連携による物体の複製。本技術により瞬時に物体の3Dモデルを取得し、3Dプリンターより出力。
関連情報
・デモあり
・展示品あり
・外国出願特許あり
- 情報
2)津波による浸水状況可視化システムの開発
福岡工業大学 工学部 電子情報工学科 教授 松木 裕二
新技術の概要
この技術では、自動車(PC)内に設置されたセンサで角速度を計測し、その解析結果に基づいて車両が津波に遭遇(浸水状態)したかを判定する。さらに、複数のPCで浸水状態が判定できれば、それらの位置情報、浸水時刻などの情報を、無線ネットワークを介して集約することで、その地域の浸水マップを作成することが可能になる。
従来技術・競合技術との比較
プローブカーによる交通流の監視技術はあるものの、津波による浸水を車両の動きで調べる研究はない。
新技術の特徴
・IoTと災害時における自動車の利点および動き方に関する特徴を組み合わせることによって、人命救助に有用な情報を提供する技術。
・浸水判定は、既存の車載装置(角速度センサ)の計測値を解析するだけで可能なため、新たなセンサの取り付けは不要。
・モバイル通信を用いた新しい応用サービスの可能性。
想定される用途
・津波による浸水のみならず、大雨による水害、土砂災害、台風被害、竜巻による被害の状況把握への応用が可能。
- 環境
3)固体触媒としてゼオライトを用いる促進酸化処理法の開発
福岡工業大学 工学部 生命環境科学科 教授 北山 幹人
新技術の概要
本技術は、固体触媒(親水性ゼオライト)の存在下で水中溶存オゾンを分解することにより、オゾンより遥かに酸化力の大きなヒドロキシラジカル等の活性酸素種を発生させ、難分解性有機物質の酸化分解反応を促進させる促進酸化処理方法(AOP)に関するものであり、既に反応速度定数が2倍になることを確認している。
従来技術・競合技術との比較
オゾンによる水処理は既に浄水処理等に広く用いられているが、オゾンとの直接反応は選択性が強く、一般に完全な酸化分解・無機化が難しい。UV等を使用する従来の促進酸化処理法は、浮遊物の多い排水処理には適用不可である。また、過酸化水素添加やpH調整、鉄イオンの添加(フェントン法)は、大量の水処理には適さない。
新技術の特徴
・通常のオゾン処理は有機物質を完全分解することはできないが、AOPは可能である。
・オゾン分解に紫外線(=エネルギー)を用いる従来のAOPに比較し、省エネルギーである。
・紫外線を用いる必要がないため濁った排水にも適用可能であり、固体触媒は繰り返し使用できる。
想定される用途
・有害な難分解性有機物質を含む排水処理
・食品製造や化成品製造工場、或いは、病院の排水処理
・浄水処理、排水リサイクルシステム
- アグリ・バイオ
4)新規分類・定量化法による食品・環境試料の簡便な微生物性検査
福岡工業大学 工学部 生命環境科学科 教授 渡邊 克二
新技術の概要
これまで遺伝子の類縁性検索は塩基配列に基づいて行われてきたが、本発明により二次情報である制限酵素切断長データからできるようになった。これにより純粋分離や遺伝子クローニングせずに微生物の同定が可能になり、最確数法と組み合わせることで、試料中の雑多な微生物群集の個々のグループを同定・定量することが可能になった。
従来技術・競合技術との比較
次世代シークエンサーを用いたパイロシークエンス法やDGGE法等の塩基配列に基づく微生物叢解析では、定量性がないためPCRリアルタイムPCRを併用したり、単純な微生物叢の流通食品でも類縁性検索を数十万分回繰り返す必要があるため、試料の微生物検査等を目的とした簡便・迅速・安価な分析方法として確立するのは困難である。
新技術の特徴
・様々な試料に含まれる主要な微生物が培養後分離せずに簡単に同定できる。
・様々な試料に含まれる雑多な微生物叢が培養法と最確数法を組みわせて同定、定量できる。
・試料から直接抽出したDNAと最確数法を組みわせて試料中の主要な微生物群集が短時間で同定、定量できる。
想定される用途
・食品、飲料製造、流通現場での衛生検査及び、多剤耐性菌の院内・院外環境への拡散状況調査への利用。
・発酵食品製造や排水処理、廃棄物処理施設の効率的運用を目的とした微生物叢診断方法としての利用。
・微生物分析専門の依頼分析業者が運用することで、上記以外の顧客の様々なニーズに応じることができる。
関連情報
・外国出願特許あり
- 機械
5)車に環境配慮型で電気エネルギを収穫する懸架装置の提案
福岡工業大学 工学部 知能機械工学科 教授 数仲 馬恋典
新技術の概要
外部から作用する機械エネルギを電気エネルギに変換できるコロイダル懸架装置を紹介する。コロイダル懸架装置とは、油圧ダンパと圧縮コイルばねから構成される従来の懸架装置に比べて、油の代わりに「水」と「ナノ多孔質シリカゲル(人工的な砂)」との混合物からなるコロイド溶液を用いた液圧シリンダである。
従来技術・競合技術との比較
懸架装置のエコ化(油が不要)、単純化(圧縮コイルばねが不要、ピストンの頭にオリフィスや弁が不要)、コンパクト化(ピストンの直径が3倍減少、シリンダの外径が60%減少)、軽量化(質量が30%減少)、アクティブ制御化(圧力の制御、表面張力の制御など)、エネルギハーベスティング化は可能である。
新技術の特徴
・低周波数、大振幅で減衰力、ばね定数、散逸エネルギが大きく、高周波数・小振幅でそれらがともに小さくなる。
・発電電力(1車あたり、10~100W)が作動圧力(20~60MPa)の変化量の二乗に比例する。
・圧力はアキシアルと同時にラジアル方向に作用するので圧電素子の最適設計により発電電力が2倍大きくなる。
想定される用途
・乗り物(自動車、バイク、鉄道、飛行機等)、構造物(建物、大型・精密機械、精密測定機器等)の懸架装置
・非空気圧タイヤのスポーク(低燃費とつながる)
・エンジン車、ハイブリッド車、EVのバッテリー充電、あるいは燃料噴射装置の電源
関連情報
・展示品あり
・外国出願特許あり
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp


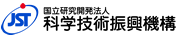
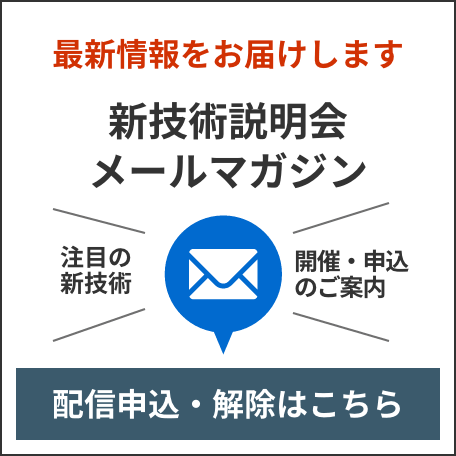
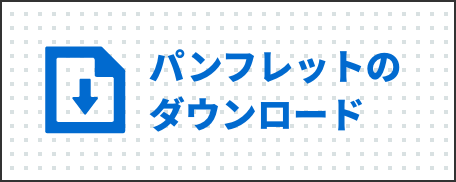
 fit.ac.jp
fit.ac.jp