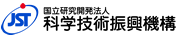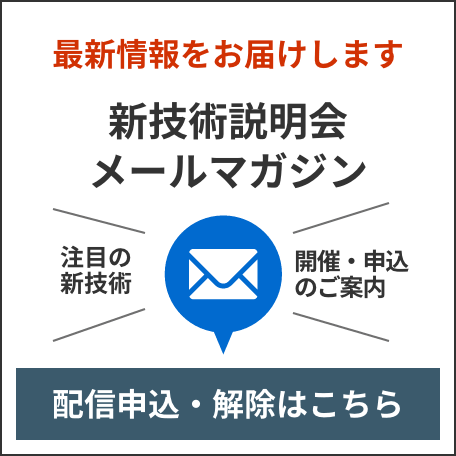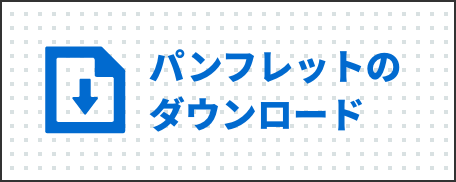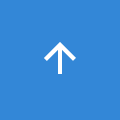工学院大学 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2024年07月11日(木) 09:55~11:55
会場:オンライン開催
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、工学院大学
発表内容一覧
発表内容詳細
- 09:55~10:00
開会挨拶
工学院大学 総合研究所 所長 小林 元康
- 10:00~10:25
- 計測
工学院大学 情報学部 情報デザイン学科 教授 田中 久弥
新技術の概要
開発された耳脳波計測デバイスは、従来の頭部キャップ型やイヤホン型と比べて装着感に優れており、耳脳波を精度良く計測できる。装着されていることを気づかれにくいため、日常的な常時脳波計測や障がい者の意思伝達などの用途に適している。耳介周辺に沿って多数の電極を配列できるため、多チャンネル化が容易で、微細電位を高精度に計測できる。
従来技術・競合技術との比較
従来の頭部キャップ型やイヤホン型の脳波計測デバイスと比較して、新技術は装着感が優れており、装着時の感覚がほとんど気づかれない。また、耳周りに配置された多数の電極により、多チャンネル化が容易で、微細電位の計測も高精度。これにより、長時間の安定した計測が可能となり、日常的な使用や障がい者の意思伝達に適している。
新技術の特徴
・装着感に優れる
・耳脳波を精度良く計測可能
・耳周りに配置された多数の電極により、多チャンネル化が容易であり、微細電位も高精度に計測可能
想定される用途
・睡眠時の脳波パターンを監視し、睡眠の質や健康状態を評価するためのデバイスとしての利用
・高齢者や身体障がい者が自在にコンピューターや周辺機器を操作できるようにするための脳波インターフェースとしての利用
・脳活動に関連する視覚刺激に対する脳の反応を測定し、視覚注意や認知プロセスの研究に貢献するためのツールとしての利用
- 10:30~10:55
- 機械
工学院大学 工学部 機械システム工学科 准教授 小川 雅
新技術の概要
X線回折法により非破壊に計測した表面の値から、内部の3次元応力やひずみを可視化することができます。加工時に生じる内部のダメージ(加工ひずみ)がわかるので、予め発生する変形を見越したり、加工条件を最適化することで高精度な加工を実現できます。機械加工だけでなく、溶接や表面改質処理なども対応可能です。
従来技術・競合技術との比較
放射光や中性子を用いれば、数ミリ~数十ミリの深さまで内部の応力やひずみを可視化できますが、大がかりな施設でのみ利用可能です。本手法は現場でも利用できるX線回折装置を使います。数値シミュレーションのように、膨大なパラメータを必要とせず、寸法と材質(ヤング率とポアソン比)がわかれば適用可能です。
新技術の特徴
・ダメージを内部まで非破壊に知ることができます
・ダメージによる変形を予測できます
・品質の可視化や修正に寄与します
想定される用途
・表面改質効果の非破壊評価
・加工による変形を見越した加工方法の決定
・3次元溶接残留応力の評価や溶接変形の予測
- 11:00~11:25
- 情報
工学院大学 情報学部 情報デザイン学科 准教授 高橋 義典
新技術の概要
小さな障害物を複数配置したブロックを使用する。ブロック背面には反射板があり、ブロックに入射した音波は反射の前後で障害物間を回折して通過する際に遅延が生じる。隣あうブロックで障害物の密度を変えることで、音響拡散体を構成する。2022年12月の新技術説明会で報告した円形の音響拡散パネルにも応用できる。
従来技術・競合技術との比較
一般的な拡散体では、数論に基づいて一見不規則な整数列を生成し、それに比例した凹凸を作ることで、様々な方向に反射波を拡散させる。これを円形にする技術について2022年の説明会で報告した。本技術は凹凸の代わりに複数の障害物を充填した領域を作る。拡散体表面の凹凸をなくし、障害物表面の拡散によって、従来より複雑な拡散が期待できる。
新技術の特徴
・複数の障害物による音速制御が応用されている
・波長に応じた凹凸がない音響拡散体
・音響レンズなどへの応用も可能
想定される用途
・コンサートホールの音響調整
・会議室、教室などの音響調整
関連情報
デモあり
- 11:30~11:55
- 環境
工学院大学 先進工学部 環境化学科 教授 赤松 憲樹
新技術の概要
分離膜を用いた水処理では、膜が汚れ分離性能が低下するファウリングが大きな問題となっている。我々は、分離膜を促進酸化水(オゾンと過酸化水素が溶解している水)へ浸漬した後に表面開始グラフト反応を行う新規技術を開発した。またこの技術を利用して低ファウリング膜を作製した。
従来技術・競合技術との比較
分離膜の表面に機能性高分子等を化学結合により修飾する方法はこれまでも様々な手法が提案されてきたが、それらの多くが減圧操作や脱酸素操作を要する技術であった。本技術は減圧操作も脱酸素操作も不要であり、スケールアップが可能な簡便な手法である。
新技術の特徴
・減圧操作も脱酸素操作も不要な膜面修飾法である
・膜面方向にも膜厚方向(細孔内部)にも均一な修飾を実現できる
・本技術でファウリング防止性を有するポリマーを修飾すると、特に溶存性有機物のファウリングを効果的に抑制する分離膜が作製できる
想定される用途
・各種水処理用分離膜、および機能性薄膜の作製
・各種機能性(無孔・多孔)材料の作製
・各種グラフト材料の作製
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
工学院大学 研究推進課
TEL:03-3340-3440
Mail:sangaku sc.kogakuin.ac.jp
sc.kogakuin.ac.jp
URL:https://www.kogakuin.ac.jp/research/collaboration/application.html
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp