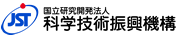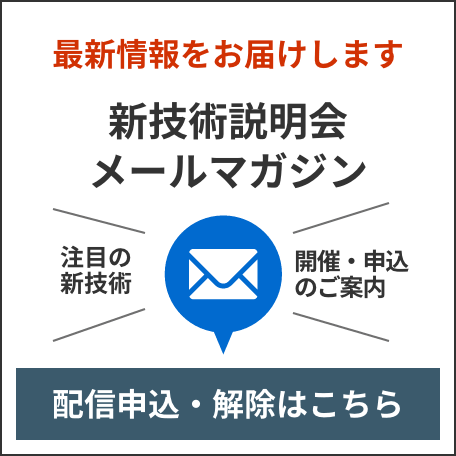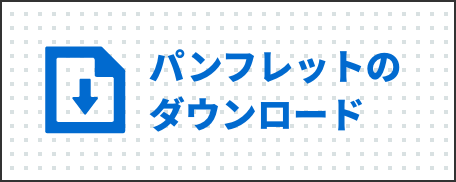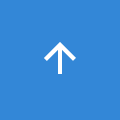理化学研究所 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2024年06月20日(木) 10:00~15:25
会場:オンライン開催
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、理化学研究所、株式会社理研鼎業
発表内容一覧
発表内容詳細
- 10:00~10:25
- 電子
理化学研究所 創発物性科学研究センター 量子電子デバイス研究チーム
チームリーダー 山本 倫久
新技術の概要
緩和せずに長距離を伝搬する電子の波束に量子情報を搭載し、電子回路において量子演算を実行する新原理の量子コンピューターです。わずか数個の基本的な演算回路で、大量の量子ビットの任意操作が可能であり、大規模量子計算の実現に適しています。
従来技術・競合技術との比較
現在開発が行われている量子コンピューターは、いずれも大型のハードウェアを必要とし、巨大な制御システムの構築が大規模化への課題となっています。本技術は、小さなハードウェアで大規模量子計算を実現する新原理の量子コンピューター技術で、1台の冷凍機とそれに付随する制御系だけで実用的な量子計算を実現できる可能性があります。
新技術の特徴
・小さなハードウェア
・大規模かつ汎用的な量子演算
・電子間相互作用や環境との相互作用に対して強靭な量子情報
想定される用途
・誤り耐性型量子コンピューター
- 10:30~10:55
- 環境
理化学研究所 仁科加速器科学研究センター 核変換技術研究開発室 室長 奥野 広樹
新技術の概要
「ヘリウム」は、MRIの冷却材や半導体製造工程の雰囲気ガス等で広く活用されていますが、近年のヘリウム輸入価格高騰等により、輸入頼みの日本では各種研究活動が阻害されています。理研が保有するヘリウムリサイクル装置(回収→精製→液化)の利用を理研外へも展開することで、国内の”ヘリウム弱者”をゼロにすることができる技術です。
従来技術・競合技術との比較
これまで同一研究機関内でのヘリウムリサイクルはありましたが、たとえば使用済MRIを回収し、ヘリウムガスを回収→精製→液化した後、新たなMRI(または別目的)で再利用、といった発想はありません。将来的にはヘリウムリサイクル装置を保有する国内の各種機関との連携やコンソーシアム化も検討中です。
新技術の特徴
・理研のヘリウム回収・液化設備のバージョンアップ
・使用済みMRIからのヘリウムリサイクル工程を確立
・国内“ヘリウム弱者”ゼロを実現
想定される用途
・ヘリウムガスのリサイクル(ガス回収→精製→液化)
・ヘリウムガス以外のリサイクル
- 11:00~11:25
- エネルギー
理化学研究所 開拓研究本部 小林固体化学研究室 専任研究員 川本 益揮
新技術の概要
ペロブスカイト化合物の化学変換特性を利用し、常温常圧でアンモニアを貯蔵する技術です。本技術の特徴は、腐食性のアンモニアを化学反応によって窒素化合物に変換した後で貯蔵するため、安全性の高い貯蔵方法です。また、窒素化合物を真空下 50 度で加熱すると逆反応が起こり、容易にアンモニアとして取り出すことができます。
従来技術・競合技術との比較
従来の多孔質化合物 (活性炭,ゼオライト,金属有機構造体など) は、アンモニアを化合物の細孔へ閉じ込めることで、常温常圧での貯蔵が可能です。しかし、これらの化合物は腐食性のアンモニアをそのまま貯蔵するため、安全性に懸念があります。また、貯蔵したアンモニアを取り出すために 150 度以上の加熱が必要です。
新技術の特徴
・常温常圧でアンモニアを貯蔵
・化学変換による安全なアンモニア貯蔵法
・繰り返し使用可能なペロブスカイト化合物
想定される用途
・アンモニアの貯蔵・運搬
・環境浄化
関連情報
サンプルあり
- 13:00~13:25
- 製造技術
理化学研究所 革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ
データ駆動型生物医科学チーム 客員研究員 沓掛 健太朗
新技術の概要
製造業でのプロセス開発にはシミュレーションが欠かせません。本発表では機械学習を活用した3つの実践的なシミュレーション活用技術を紹介します。①多様な誤差を考慮しながらシミュレーション内のパラメータを調節する方法。②製品品質に影響のある構造を特定しながら製造装置を設計する方法。③エンジニアの知識に基づいて製造条件を最適化する方法。
従来技術・競合技術との比較
①従来の単純なパラメータ最適化では無理に合わせこむ場合があり、未知の条件への予測精度に課題があった。②膨大な装置設計変数から製品品質に影響する構造パラメータを特定して最適化することが困難であった。③最適化の目的関数を数式化することや重み付けすることが困難であった。
新技術の特徴
・実際に起こりうる誤差(ばらつき)を考慮することで合理的なシミュレーション結果を得ることができます
・装置構造最適化において、重要構造の特定、計算時間の短縮、シミュレーション回数の削減が可能になります
・エンジニアが思い描く理想的な状態を実現する製造条件を得ることができます
想定される用途
・シミュレーションモデル開発、ロバスト評価・設計、シミュレーションと実験の融合
・設計者の支援ツール、装置設計の自動化
・熟練技術者の知識のデータ化、見える化、継承とその知識を活かした最適化
関連情報
デモあり
- 13:30~13:55
- 情報
理化学研究所 革新知能統合研究センター 目的指向基盤技術研究グループ 音楽情報知能チーム
チームリーダー 浜中 雅俊
新技術の概要
高速飛行するティルトウィング型ドローンの運用を想定し、AIを活用した基盤技術を構築してきた。ドローンは、山岳地帯では衛星からのGPS信号が遮蔽され非GPSになりやすい。GPS信号を得ようと上昇するためには大きなエネルギーが必要でエネルギー効率が悪くなる。ドローン配送を考えた場合には、荷物を格納するなどの機構が必要となる。
従来技術・競合技術との比較
高速で自律飛行するドローンは自己位置の把握が必須である。GPSは、山やビルなどにより遮蔽されると精度が低下し測位が不能になる。可視光カメラ等による位置検出は夜間に使うことができない。飛行効率を最適化する目的で、ドローン飛行網(ドローンハイウェイ)を設計・構築する手法は提案されていない。
新技術の特徴
・非GPS時における飛行エリア・飛行方向検出
・ドローンを高エネルギー効率で運用する最適経路網構築手法
・ティルトウィング型ドローンの機構
想定される用途
・山岳地帯などでの配送
・災害時の状況把握
・救急・救命ドローン
- 14:00~14:25
- 医療・福祉
6)エネルギーランドスケープによる健康・疾患状態の可視化
発表資料理化学研究所 情報統合本部 先端データサイエンスプロジェクト 医療データ数理推論チーム
客員主管研究員 石川 哲朗
新技術の概要
健康診断や医療検査の結果は数値などが羅列された多次元データであり、一部の専門家以外には読み解くのが難しい。そこで本技術は誰でも直感的に健康・疾患状態を把握できる地形図による可視化を実現する。さらに、状態の変化を地形図上の軌跡として示すことで疾患の発症予測や病態推移を理解するツールとしても有用である。
従来技術・競合技術との比較
健診結果を可視化するダッシュボードや疾患発症の予測ツールは多く開発されている。しかしそれらは個別の項目にのみ着目するものや、予測結果を表示するのみの機能に特化したものが多い。一方で本技術は検査項目の相互作用を考慮した総合的な評価を行える。さらに状態を地形図として可視化することで高い説明性も実現する。
新技術の特徴
・状態の安定性を統計物理学に基づくエネルギーにより定量化し地形として描出
・状態の遷移パターンを地形図上に描画して直接目で見て理解することが可能
・健康・医療分野に限らず、多変数の相互作用を考慮した正常・異常状態のクラスタリングであればどのようなドメインにも応用できる
想定される用途
・健康診断や臨床検査結果を被験者に説明するツールやヘルスケアアプリ
・医療者や研究者が患者の健康状態を把握しモニタリングするためのツール
・健康問題や疾患に対する治療・介入の予測や意思決定の支援技術
- 14:30~14:55
- 医療・福祉
理化学研究所 放射光科学研究センター 利用システム開発研究部門
物理・化学系ビームライン基盤グループ
放射光イメージング利用システム開発チーム
チームリーダー 香村 芳樹
新技術の概要
X線照射で可視発光する微小シンチレーター材料を結合させた生体試料を作成し、幅60ナノメートル程度のX線ライトシートを照射する。X線光軸と直交させた可視光顕微鏡で観察し、試料走査により、高奥行き解像度で、微粒子の三次元分布を計測できる。構造光照射も検討している。
従来技術・競合技術との比較
X線ライトシートで65nm厚(半値全幅)程度の奥行き幅が達成され、可視光ライトシートの最小400nm厚程度を上回る。面内方向の分解能については、孤立粒子であれば重心計算による解像度改善が可能だが、密集した試料で可視光顕微鏡の解像度 (400nm)程度を上回った解像度を得るため、構造光照射も検討している。
新技術の特徴
・X線ライトシート顕微鏡を用いた三次元イメージングは、常に、奥行き方向の解像度が面内方向を上回るユニークな特徴を有する。5ミクロン厚の細胞を測る際には、可視光ライトシート顕微鏡では最大10スライス程度でしか観察できないが、100スライス程度での観察が可能となり、微細構造を観察するのに役立つ。
・X線ライトシート顕微鏡観察で観察に用いる可視光顕微鏡は、他の蛍光顕微鏡観察と共通化可能であり、試料の透明化の技術なども併用可能である。これらを駆使して新しい付加価値を持つ画像取得が容易である。
・X線は透過能が高いため、厚みを持った器官の内部構造の可視化が可能である。
想定される用途
・細胞、オルガネラ内の高分子、薬剤分子の分布などを複数色で可視化
・厚みを持った器官の内部構造の可視化
- 15:00~15:25
- 計測
理化学研究所 創発物性科学研究センター 電子状態マイクロスコピー研究チーム
チームリーダー 于 秀珍
新技術の概要
本技術は最先端三次元顕微計測技法を提供する。この技法を用いることで、ナノメトールスケールでの電子スピンテクスチャの三次元マッピングが可能となり、これにより新たな磁性科学の学理の構築に貢献できるだけでなく、電子スピンを利用するスピントロニクスの開拓にも導くことが出来る。
従来技術・競合技術との比較
三次元結晶構造の可視化や生体イメージングなど広く使われた技法はX線トモグラフィーがあるが、三次元電子スピンの微細構造の可視化には高い空間分解能が求められる。そのため、電子線ホログラフィックトモグラフィーが開発されたが、この方法は煩雑なデータ記録プロセスに数時間から数日までかかる。一方で、本特許はデータ取得の時間を十数分間に大幅に短縮するだけでなく、データの構築アルゴリズムの有効性を高め、空間分解能も5ナノメートル以下に改善し、さらなる電子スピンの微細構造を正確な可視化が可能となる。
新技術の特徴
・高空間分解できる三次元顕微技術
・短時間で正確に三次元電子スピンテクスチャの微細解析
・材料やデバイスを非接触でその三次元情報を計測できる
想定される用途
・ナノメートル磁気構造の顕微技法
・三次元電子デバイスの微細構造の観察
・材料科学の構築
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
株式会社理研鼎業(理化学研究所新技術説明会事務局)
TEL:048-235-9308
Mail:senryaku innovation-riken.jp
innovation-riken.jp
URL:https://www.innovation-riken.jp/
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp