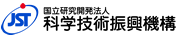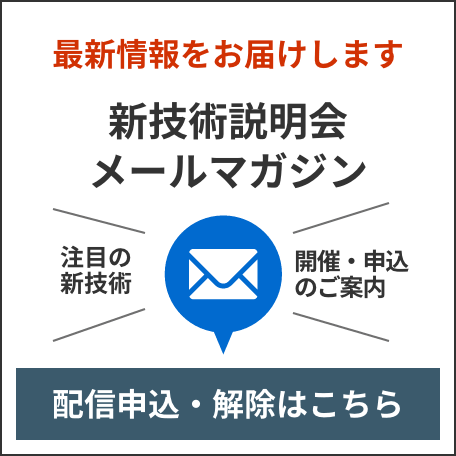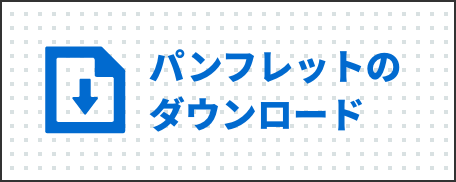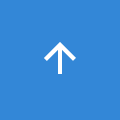JST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)②~ICT、電子デバイス、ものづくり、機能材料、アグリ・バイオ~ 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2025年11月18日(火) 13:00~15:25
会場:オンライン開催
参加費:無料
主催:科学技術振興機構
発表内容一覧
発表内容詳細
- 13:00~13:25
- デバイス・装置
東北工業大学 工学部 電気電子工学課程 教授 室山 真徳
新技術の概要
我々は、省配線接続かつイベントドリブンによる高速応答可能な多数個実装型の触覚センサデバイス・システムと高度な認識システムを、独自開発の専用LSIとMEMS・PCBプロセスを基に開発した。また、短TATで少数個製造可能でPoC向きであるPCB型触覚センサと、量産向きのMEMSプロセス型センサを有する。
従来技術・競合技術との比較
従来の触覚センサは、センサ数が限られ、配線が煩雑でリアルタイム性に課題があり多数個のセンサを任意の箇所に配置することが難しい。我々の技術は、多点・高密度/任意配置に対応し、耐故障性や拡張性にも優れる点で競合に対し優位性を持つ。
新技術の特徴
・多数個の触覚センサデバイスの設置(省配線、高速応答)
・アプリ探索用体制(PCB型触覚センサ)と量産体制(ウェハプロセス)の確立
・センサ故障やセンサ劣化に対応
想定される用途
・ロボットへの触感付与(製造現場、農業・漁業、介護現場)
・装着型デバイスへの接触センサ付与(外骨格デバイス、センサグローブ)
・物流
関連情報
・サンプルあり
・デモあり
・展示品あり
- 13:30~13:55
- 材料
物質・材料研究機構 磁性・スピントロニクス材料研究センター グリーン磁性材料グループ
主席研究員 寺田 典樹
新技術の概要
主に医療用MRIなどに広く用いられている今日の極低温冷却技術は、ヘリウムや重希土類元素といった希少資源に強く依存している。本研究では、希土類元素を含まない材料として初めてヘリウム液化温度(マイナス269℃)以下の温度で機能する、環境負荷が少なく持続的な極低温冷凍機用の蓄冷材を開発した。
従来技術・競合技術との比較
1990年代から今日に至るまで、極低温冷却用冷凍機の蓄冷材は重希土類元素を含む材料が用いられてきた。今回我々は、スピン間相互作用の競合効果の結果として現れる、大きな磁気比熱の利用によって、銅、鉄、アルミというありふれた元素で構成された、持続的で安価な蓄冷材料を開発した。
新技術の特徴
・持続的な極低温度冷却用蓄冷材
・偏在する希土類資源を含まない
想定される用途
・MRI用超伝導マグネットの冷却
・量子デバイスの冷却
・液体水素冷却
- 14:00~14:25
- 材料
3)Sc系窒化物が拓く次世代エレクトロニクス:耐熱性に優れた不揮発性メモリなどへの応用展開
発表資料産業技術総合研究所 センシング技術研究部門 上級主任研究員 上原 雅人
新技術の概要
GaNやAlNはScNとの固溶化で優れた強誘電体となる。大きな残留分極、1000℃以上の高耐熱性、150℃以下の低温製膜でCMOS適合性を持つ。我々はスイッチング電界を6割低減し、低消費電力化に目途を付けた。不揮発性メモリなどへの新しいエレクトロニクスへの展開が期待される。
従来技術・競合技術との比較
無機系強誘電体として最も知られるPb(Zr、Ti)O2はナノレベルの微細化で機能が消滅。不揮発性メモリへの開発が進むHfO₂系は準安定相で信頼性に課題があり。また、これらの作動限界温度は400℃以下。Sc系窒化物は安定で1000℃での作動報告あり。HfO₂系の4倍の高い残留分極は記憶容量の高密度化も可能。
新技術の特徴
・HfO₂系の4倍以上の残留分極と低抗電界による低消費電力動作の新しい不揮発性メモリの可能性
・優れた耐熱性(1000℃でも作動)
・スパッタリング法による低温製膜(150℃以下)でCMOSプロセス適合性あり
想定される用途
・IoTエッジデバイス向けの不揮発性メモリ、ストレージ、センサ
・高周波フィルタ
・GaN-HEMTや非線形光学素子など、分極反転を活用した素子
- 14:30~14:55
- 創薬
群馬大学 大学院理工学府 物質・環境部門(応用化学プログラム) 教授 吉原 利忠
新技術の概要
マイクロプレートリーダーの時間分解発光測定機能を用いて、細胞内酸素濃度(分圧)をリアルタイム計測するための酸素プローブを開発した。細胞内に分布する酸素プローブの発光寿命変化から、外部刺激による細胞呼吸に依存した酸素分圧変化を簡便に定量化できる。
従来技術・競合技術との比較
従来の酸素プローブは、細胞親和性が低いため試薬を添加してから14時間以上培養する必要がある。また、励起波長として380nmの紫外光が必要であり、細胞への光毒性が懸念されている。これに対して、本発表で紹介する酸素プローブは細胞移行性が高く30分間の培養で測定が可能であり、また、480nmの可視光で励起できる。
新技術の特徴
・マイクロプレートリーダーだけでなく、蛍光顕微鏡などのイメージング機器でも計測可能
・スフェロイドなどの3次元細胞系でも評価可能
・バイオ計測以外の酸素センサーとしても使用可能
想定される用途
・ライフサイエンス研究における細胞評価ツール
・食品包装材の酸素透過性評価
・河川や湖底の酸素濃度計測、風洞実験における感圧センサー
- 15:00~15:25
- アグリ・バイオ
岩手大学 農学部 地域環境科学科森林科学コース 准教授 阪上 宏樹
新技術の概要
密度の高い木材は建築材や家具材等に利用されますが、密度の低い木材はあまり利用されません。本研究では木材の利用促進のため、低密度の木材を軟化させてスポンジ状態に改質する開発を行いました。これまでに無い木材の性能を皆さんに知って頂き、固定概念にとらわれない新たな木材利用の可能性を期待しています。
従来技術・競合技術との比較
本技術は特殊な機械や知識も必要無く、誰でも簡単に製造可能な方法で生産することができます。木材本来の材質をそのまま利用しますので、木材らしい外観を維持したまま、使用する木材(樹種や産地)に応じて、工業製品にはない、ユニークな特徴を引き出すことが可能です。
新技術の特徴
・木材のスポンジ化
・木材の湾曲、折り曲げ
・軟化木材
想定される用途
・建築内装材
・クッション材
・アパレル製品
関連情報
・サンプルあり
・展示品あり
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
科学技術振興機構 スタートアップ・技術移転推進部 研究支援グループ
TEL:03-5214-8994
Mail:a-step  jst.go.jp
jst.go.jp
URL:https://www.jst.go.jp/a-step/
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp