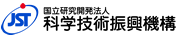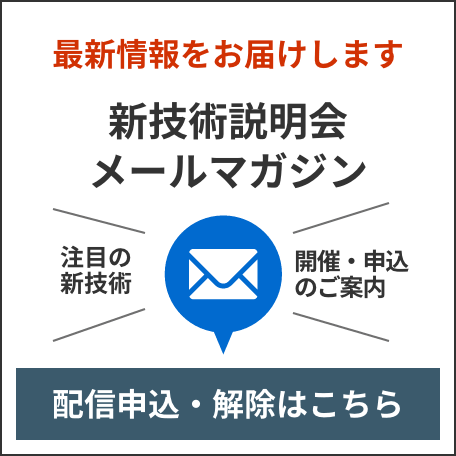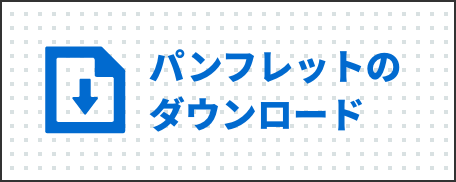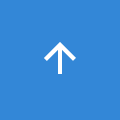電気通信大学 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2025年05月13日(火) 11:00~15:25
会場:オンライン
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、電気通信大学
後援:一般社団法人目黒会(電気通信大学同窓会)、多摩信用金庫、
一般社団法人首都圏産業活性化協会(TAMA協会)、株式会社キャンパスクリエイト
発表内容一覧
発表内容詳細
- 11:00~11:25
- 機械
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 教授 守 裕也
新技術の概要
流れの中に発生する乱流をリアルタイムで予測する技術です。高精度なシミュレーションと非線形な予測手法を組み合わせることで、事前の情報がなくても乱流の変化をとらえます。予測に基づき乱流を打ち消すように制御を与えれば、乱流による抵抗を抑えることができます。
従来技術・競合技術との比較
従来の乱流制御では、事前に多くの流れのデータや知識を準備する必要があり、新しい状況には対応しにくい問題がありました。本技術は、流れのその場の情報から直接予測・制御を行えるため、さまざまな状況に柔軟に対応できます。
新技術の特徴
・事前データ不要:未知の流れでもリアルタイムに予測・制御が可能
・小さな空間でも効果を発揮:局所的な流れの乱れに対応できるため、狭い配管や機器内部でも使える
想定される用途
・航空機や自動車の空気抵抗の低減
・工場の配管内の流体制御によるエネルギー効率向上
・サーバールームなどの冷却効率改善による電力削減
- 11:30~11:55
- 製造技術
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 准教授 梶川 翔平
新技術の概要
偏心拡管プラグを管に通して引き抜くことによって、周方向に肉厚分布を有する偏肉管を成形する。拡管にともなって、管の肉厚は減少する。偏心拡管プラグを用いると、肉厚の減少量が周方向で変化するため、周方向に肉厚分布が生じる。プラグの偏心量を調整することによって、成形品の偏肉率をコントロールすることが可能である。
従来技術・競合技術との比較
偏肉管の製造方法は確立していない。偏肉管の製造方法の一つとして、切削加工が挙げられるが、加工に時間がかかるため、大量生産が難しく、歩留まりも悪い。また、一般的な縮管型の抽伸加工と比較すると、拡管型の場合は周方向に引張応力が作用するため、偏肉しやすい応力状態である。
新技術の特徴
・周方向に肉厚分布を有する偏肉管を簡便かつ生産性の高い方法で製造できる。
・プラグの偏心量を調整することによって、成形品の偏肉率をコントロールできる。
想定される用途
・曲げ加工を想定した一次加工。偏肉管の厚肉部を曲げ外側とすることによって、加工時の割れを抑制できる。
・自動車の骨格部品としての利用。例えば、衝突時に圧縮側となる部分を厚肉部にすることによって、部材料の高強度化や軽量化が期待できる。
関連情報
・サンプルあり
- 13:30~13:55
- 計測
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 教授 木寺 正平
新技術の概要
ミリ波車載レーダは視界不良状況でもセンシングが可能であるが、空間(水平方向)分解能が不十分であるため、特に前方の歩行者を識別することが難しい。これを解決するため新技術では、人体形状に特化したスパースアレイの設計法を提示し、かつ、レーダ移動を活用した合成開口処理を用いた虚像抑圧法を提案している。
従来技術・競合技術との比較
車載ミリ波レーダの空間分解能を高めるには、アレイの開口面積を増やす必要があるが、半波長以上の間隔で配置すると虚像が生成される問題があった。またレーダの移動による合成開口処理によって空間分解能を高める方法もあるが、目標が前方にある場合は、空間分解能を改善することができないという課題があった。新技術では、前方の歩行者の空間分解能を高めるために、人体形状に特化した最適化アレイを導入し、かつ、合成開口処理による虚像抑圧を導入することで、従来技術の課題を本質的に解決することができる。
新技術の特徴
・人体形状に特化したスパースアレイで前方の歩行者を高分解能に画像化可能
・ハードウェアの改良なしで、データ解析(ソフトウェア)のみで、画像化精度及び空間分解能を高めることができる
・圧縮センシング等の計算コストが高い手法に比べて、短時間で画像化が可能
想定される用途
・車載搭載型の周囲センシング技術
・交通インフラ搭載型の夜間・悪天候下での歩行者・自動車識別技術
・ミリ波非接触バイタルサインにおける高分解能画像化とデータ分離
- 14:00~14:25
- 医療・福祉
電気通信大学 環境安全衛生管理センター 准教授 北田 昇雄
新技術の概要
ホタルなどの発光生物が示す発光現象は、生体内の様々な現象を観察可能な生体イメージングシステムとして広く応用されています。私たちは、発光基質の構造を改変することで、発光強度、波長、選択性などの特性を制御した発光材料を開発しました。これにより、多様な生命現象を可視化できるシステムの開発が期待できます。
従来技術・競合技術との比較
従来技術では、黄緑色や青色など特定の発光波長に限定され、観察可能な生命現象が限られていました。一方、本技術はホタルや海洋発光生物の発光材料の構造を改変することで、発光強度、波長、選択性などの発光特性を制御した材料を開発しました。そのため、観察したい現象に最適な材料を選択可能です。
新技術の特徴
・発光特性を制御可能な材料
・可視光を網羅する多色の発光材料
・特異的に発光する材料
想定される用途
・生体イメージング
・診断技術
・環境測定
関連情報
・サンプルあり
- 14:30~14:55
- 医療・福祉
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 機械知能システム学専攻 准教授 小泉 憲裕
新技術の概要
本技術では臓器内に包含された患部の位置と広がりを精確に診断(局在診断)・局所的に治療することで機能の温存を最大限可能とする局在診断・局所治療支援システムを新規に提案、その開発を目的とする。
従来技術・競合技術との比較
従来技術ではMRIの情報をTRUS画像に融合する際、臓器内に包含された患部のリアルタイムな変形に対応することができないという課題があるのに対し本技術ではこれに対応することができる。
新技術の特徴
・臓器内に包含された患部の位置と広がりを精確に診断(局在診断)
・局在診断に基づいて局所的に治療することで機能の温存を最大限可能とする
・術中のリアルタイムな患部の変形に対応することができる
想定される用途
・臓器内に包含された患部の位置と広がりをリアルタイムで精確に診断(局在診断)
・局所治療における患部の変形を考慮したモニタリング
・生検における患部の変形を考慮したモニタリング
- 15:00~15:25
- 情報
電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報学専攻 教授 橋本 直己
新技術の概要
プロジェクションマッピング(特許1)や多視点ディスプレイ技術(特許3)を応用して、視野を覆い尽くす頭部搭載型ディスプレイを実現する。また、既存の液晶ディスプレイの構造を応用して、見切れない広視域な立体ディスプレイ(特許2)を実現する。いずれも映像への臨場感や没入感を大幅に向上させる。
従来技術・競合技術との比較
特許1及び3では、重量をほとんど変えずに、全視野を覆えるように映像提示領域を拡張する。特に特許3では、誰もが所持するスマートフォンを利用することで、頭部搭載型ディスプレイの普及促進にも寄与する。特許2では、従来の立体ディスプレイでは実現できなかった広い視域を実現する。
新技術の特徴
・プロジェクションマッピングと頭部搭載型ディスプレイの融合
・多視点ディスプレイを頭部搭載型ディスプレイの提示視野拡大に活用
・既存液晶ディスプレイの構造を利用して、見切れない広視域な立体像提示を実現
想定される用途
・装着負担の少ない全視野を覆い尽くす頭部搭載型ディスプレイ
・スマートフォンを使った安価な超広視野な頭部搭載型ディスプレイ
・周囲から取り囲んで観察可能なテーブルトップ型裸眼立体ディスプレイ
関連情報
・デモあり
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
電気通信大学 産学官連携センター
TEL:042-443-5871
Mail:onestop  sangaku.uec.ac.jp
sangaku.uec.ac.jp
URL:https://www.uec.ac.jp/inquiry/new/8
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp