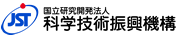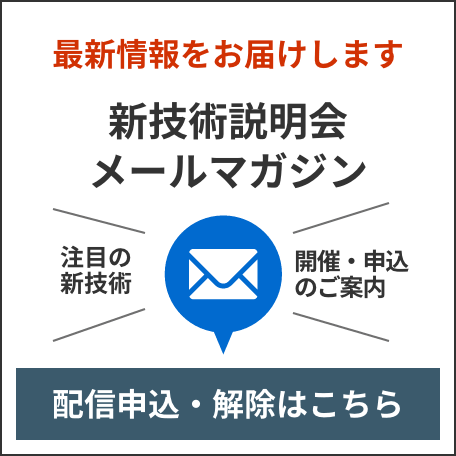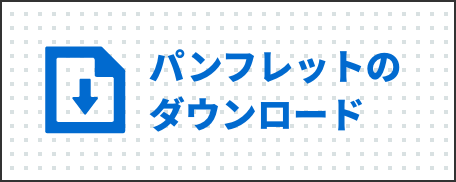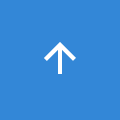関西8私大 材料&計測 新技術説明会【オンライン開催】
日時:2025年03月13日(木) 10:00~14:55
会場:オンライン開催
参加費:無料
主催:科学技術振興機構、摂南大学、関西大学、
近畿大学、大阪産業大学、関西学院大学、甲南大学、
龍谷大学、大阪工業大学
発表内容一覧
発表内容詳細
- 10:00~10:25
- 材料
関西大学 システム理工学部 物理・応用物理学科 准教授 本多 周太
新技術の概要
縦型の長い強磁性柱に複数の磁化(情報)を縦にならべて情報配列とする不揮発メモリ。柱上部には磁気抵抗素子が設置され、柱上端の情報を磁気抵抗で読み出す。柱上から下に電流を流すことで、柱の情報が上側へシフトし、柱下部には新たな情報が書かれる。電流の向き・大きさ固定で、読み出し書き込みを制御可能である。
従来技術・競合技術との比較
DRAMと比べて、低速動作であるが、多ビット・不揮発な点で有利。フラッシュメモリと比較して、高速動作・高書換え耐性・簡易な回路で動作可能。記録密度は同等。磁気メモリと比較して、簡易な回路、1電流動作、高密度。これまで製品化しているメモリ全体と比較すると、動作回路が単純で記録密度が高い。
新技術の特徴
・1つの向きと大きさの電流で不揮発記憶デバイスを制御可能
・1素子あたり多ビットで2端子なため回路が単純
・破壊読み出しなので情報を完全に消すことが可能
想定される用途
・不揮発性メモリ
・人工ニューロン
- 10:30~10:55
- 材料
近畿大学 農学部 生物機能科学科 講師 岡村 大治
新技術の概要
がん細胞を含むあらゆる動物細胞を増殖させる際に通常用いられるウシ胎児血清(血漿成分)は高コストの原因であり、安全性・倫理的な課題も抱えている。本技術は骨格筋細胞の培養を無血清化する技術である。哺乳動物やニワトリの骨格筋細胞に有効であり、無血清条件における骨格筋細胞の増幅技術を確立した。
従来技術・競合技術との比較
従来より、骨格筋細胞の増幅技術は、ウシ胎児血清を含む血清培地に依存しており、無血清もしくは低血清条件下では速やかにその増殖性を失ってしまう。我々は培養液に加える添加物を工夫することで、血清にも薬剤にも依存しない安全性の高い筋芽細胞の無血清化を実現した。
新技術の特徴
・骨格筋細胞の培養による増幅を実現
・培養液を無血清化したことで、コスト・安全性・倫理的な課題を克服
・動物性成分を排除することで、ヒトへの移植を実現可能に
想定される用途
・家畜の骨格筋細胞を用いた培養肉の生産(培養ステーキ肉を実現へ)
・筋疾患患者の骨格筋細胞を体外で増幅し、患者に戻すことで回復を促す
・安全で拒絶反応のない美容・アンチエイジング施術の材料を提供
- 11:00~11:25
- 材料
大阪産業大学 工学部 電気電子情報工学科 教授 草場 光博
新技術の概要
材料表面にナノ秒紫外レーザーを照射することで結晶性を保持した状態で先端が20nm程度のナノドット構造を均一かつ高密度に形成させ、ナノドット構造の先端に圧縮応力を付与させることに成功した。この技術をシリコン太陽電池に適用することで太陽光の無反射化、圧縮応力によるバンドギャップ制御などの機能性を付与することで高効率化の技術として期待される。
従来技術・競合技術との比較
従来、材料表面に圧縮応力を付与する方法としてピーニング技術があるが、処理前の結晶構造を保持させることができず、結晶性が重要とされる半導体材料や誘電体材料等には適用できなかった。この技術は結晶性を保持した状態で圧縮応力を付与することが可能となり、固体材料全てに付与できると期待される。
新技術の特徴
・表面圧縮応力付与
・無反射化
・バンドギャップ制御
想定される用途
・シリコン太陽電池の高効率化
・材料の無反射化
・耐放射線性
- 12:30~12:55
- 計測
関西学院大学 工学部 電気電子応用工学科 准教授 吉田 浩之
新技術の概要
液晶の配向パターニングにおいて、透過型回析素子を構成する表・裏の配列の構造周期と構造傾斜角の設計条件を明らかにすることで、特定の波長帯域でのみ動作する透過型回析素子を実現する技術です。
従来技術・競合技術との比較
従来の大型のバルク型光学素子に比べ、本技術は薄膜で軽量な構造となっています。またネマティック液晶を用いた透過型回折光学素子は、通常、入射する全波長に対して回折を生じるため、波長毎に回折角が変化して色収差が発生するという課題がありますが、本技術は波長選択性を持つため、複数の構造を積層することで、色収差を補償した素子の実現が可能です。
新技術の特徴
・薄くて軽量な小型の回折光学素子の具現化
・波長選択性を有した透過型回析素子
・光学デバイスの小型化
想定される用途
・スマートグラスなど小型軽量な次世代表示ディスプレイ
・レーザ光を用いる機器(レーザ送・受信機等)の分光素子
・光を用いる機器(太陽光発電装置、カメラ等)の光学素子
- 13:00~13:25
- 計測
甲南大学 フロンティアサイエンス学部 生命化学科 准教授 臼井 健二
新技術の概要
本発表では、特にマイクロビーズなどの固相担体に固定化したペプチド(小タンパク質)ビーズを用いた分析装置開発について紹介する。このペプチドビーズは従来、固定化していないペプチド溶液では不可能・困難であった諸問題を解決でき、医療、環境分野での分析に応用できる。
従来技術・競合技術との比較
ペプチドビーズの取り扱いはフィルター付きカラムなどを用いることで比較的操作性に優れており、さらに色素などを用いた分光分析技術とを組み合わせることで、従来技術・競合技術と比較して、簡便に必要かつ十分な分析情報を得ることが可能となっている。
新技術の特徴
・混合物から目的分子のみを選択的に濃縮し、分析することが可能
・ペプチド配列を変更すれば他の目的分子の分析にも応用できる
・固定化ペプチドは分析だけではなく、ペプチド薬剤などの創出にも役立つ
想定される用途
・環境中重金属、放射性物質などの現場での簡易測定
・化学製品・化学物質・混合物におけるアレルギー性の有無の判定
・血液、唾液などを用いた病気の早期診断
- 13:30~13:55
- 計測
龍谷大学 先端理工学部 電子情報通信課程 教授 石崎 俊雄
新技術の概要
高効率な電力増幅器の設計に向け、測定できる反射係数の領域が限定されず、また、大きな反射領域で反射係数が1を超えないようにし、安定的に測定でき、システムとして簡素化及び低コスト化が可能なアクティブロードプル測定システムを提供する。
従来技術・競合技術との比較
開ループ型のアクティブロードプル測定システムでは、スミスチャート全域を測定するには、振幅と位相を細かなステップに設定して、その組み合わせ点で測定を行わなければばらない。一方、閉ループ型では反射係数が1を超えないようにする必要がある。よって、システムの制御が複雑になる。
新技術の特徴
・大きな反射領域での測定が可能
・リアルタイムで観測が可能
・大幅な小型化、低コスト化
想定される用途
・マイクロ波加熱装置の開発
・無線電力伝送用高周波電源の開発
・無線通信装置の開発
関連情報
サンプルあり
- 14:00~14:25
- 計測
大阪工業大学 工学部 応用化学科 講師 松村 吉将
新技術の概要
ビスマス-ジチオカルボキシレート錯体化合物を合成したところ、この化合物自体は非蛍光性だが、フッ化物イオンと反応することで蛍光発光性へと変化することが明らかになった。また、フッ化物イオンに対する高い選択性も有していたことから、フッ化物イオンの簡易検出剤として期待できる。
従来技術・競合技術との比較
ターンオフ型の蛍光発光によるフッ化物検出材料は多数報告されているものの、より目視で認識しやすいターンオン型の蛍光発光物質は報告例が限定的である。また、フッ化物イオンとその他のイオンの差別化が困難なケースが多い中、本技術はフッ化物イオンに対する高い選択性を有している。
新技術の特徴
・ターンオン型蛍光発光
・フッ化物イオン選択性
想定される用途
・フッ化物イオンの検出
- 14:30~14:55
- 計測
摂南大学 理工学部 電気電子工学科 准教授 西 恵理
新技術の概要
母体(乳房)への接触力・接触タイミングを柔軟に設定することができる「母乳を摂取する乳児の舌運動を模擬した技術」である。本技術の適用により、最適な母乳搾出手法を探る上で繰り返し再現性の高い実験が可能となる。効果的な搾出手法を見出した後は、従来にはなかった母体に優しい搾乳器の大量生産が期待できる。
従来技術・競合技術との比較
従来の搾乳器は大きな圧力を加え吸引する搾出手法や所定位置で運動を発生させる手法が主であり、一般的には母体に痛みを伴うものであった。しかし、実際の乳児は蠕動様運動と呼ばれる舌をうねらせる運動により母乳を搾出している。本技術はその舌運動を模擬した機構の再現を通じて、母体に優しい母乳搾出を実現するものである。
新技術の特徴
・乳児の舌運動を模した動作を人工的に発生させることで、効果的な母乳搾出を実現
・搾乳機能の評価を繰り返し行うことが可能
・他の哺乳類に応用可能な構造
想定される用途
・搾乳器
・哺乳時の口腔内機構を有する乳児モデル
・液体搾出装置
お問い合わせ
連携・ライセンスについて
摂南大学 研究支援・社会連携センター
TEL:072-800-1160
Mail:SETSUNAN.Kenkyu.Shakai josho.ac.jp
josho.ac.jp
関西大学 研究支援・社会連携グループ
TEL:06-6368-1245
Mail:sangakukan-mm ml.kandai.jp
ml.kandai.jp
近畿大学 大学運営本部学術研究支援部
TEL:06-4307-3032
Mail:kenkyujosei itp.kindai.ac.jp
itp.kindai.ac.jp
大阪産業大学 社会連携・研究推進センター
TEL:072-875-3001
Mail:sangaku cnt.osaka-sandai.ac.jp
cnt.osaka-sandai.ac.jp
関西学院大学 研究推進社会連携機構事務部
TEL:079-565-9052
Mail:industry-academia kwansei.ac.jp
kwansei.ac.jp
甲南大学 フロンティア研究推進機構事務室
TEL:078-435-2559
Mail:sangaku ml.konan-u.ac.jp
ml.konan-u.ac.jp
龍谷大学 知的財産センター事務部
TEL:077-544-7270
Mail:chizai @ad.ryukoku.ac.jp
@ad.ryukoku.ac.jp
大阪工業大学 学長室 研究支援社会連携推進課
TEL:06-6954-4140
Mail:oit.kenkyu josho.ac.jp
josho.ac.jp
新技術説明会について
〒102-0076 東京都千代田区五番町7 K’s五番町
TEL:03-5214-7519
Mail:scett jst.go.jp
jst.go.jp